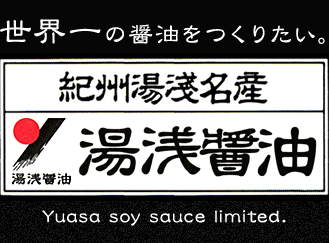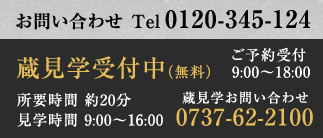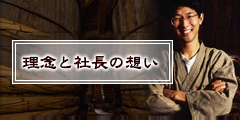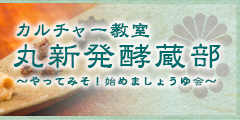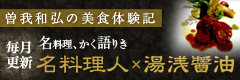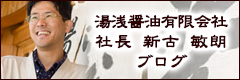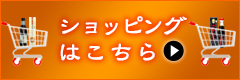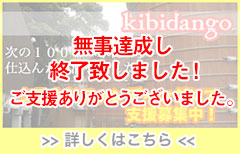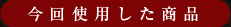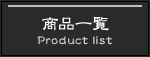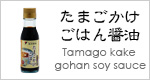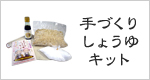141 2025年07月関西は古くからの酒どころで、伊丹郷は灘五郷と並んで江戸市中で〝下り酒″と高く評された産地である。伊丹郷を代表する日本酒メーカーが「山は富士なら、酒は白雪」のフレーズで有名な小西酒蔵だ。そんな小西酒蔵がクラフトビールをお目見得させたのは平成7年(1995)の事。ベルギービールのエッセンスが入った「白雪ビール」は、今や全国の地ビールの代表格でもある。清酒「白雪」と「白雪ビール」が楽しめる「白雪ブルワリーレストラン長寿蔵」を久しぶりに訪れた。地ビールに合う料理を味わいたいのが本音だが、仕事柄いつものアレ(・・)をやらねばならない。同店の合志達矢店長にお願いし、湯浅醤油・丸新本家の商品を使った私だけのスペシャリテを取材用に作ってもらった。さて「長寿蔵」の料理人達は、いかになる料理表現をしたのであろうか。
白雪ブルワリーレストラン長寿蔵 合志達矢
(「白雪ブルワリーレストラン長寿蔵」店長)
 「伊丹の地ビールを楽しむべく
「伊丹の地ビールを楽しむべく
『柚子梅つゆ』や『赤みそ』
を使って料理長らが
当店らしい料理に仕上げました。
苦みの少ないエールタイプにマッチしたのではないでしょうか」
伊丹市民に愛されたブルワリーレストラン



令和2年(2020)の日本遺産に〝「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷″が認定された。日本遺産とは地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するもの。その認定は、伊丹や西宮・神戸で古くから行われている日本酒づくりが高く評された事によるものだ。灘五郷の酒づくりは、江戸期から有名で、樽回船で江戸まで運ばれた事によって灘の酒が江戸庶民間でブレイク。いいもの下り酒と称す事から派生し、質の落ちる酒を〝下らない″と揶揄し、「くだらない」なる言葉まで生んでしまった。下り酒はなくなったものの、今でも「くだらない」の例えだけは残っているのだから面白い。下り酒と江戸で人気を博したのは、何も灘の生一本だけではなく、日本遺産にもあるように伊丹諸白も同様に高い評価を受けていた。伊丹諸白とは、清酒が伊丹で初めて誕生したのに関する言葉で、伊丹の酒は麹と掛米両方に精酒米を惜しみなく使った事による。灘が男酒らしくすっきりした切れのある味を生一本と呼んだのと同じように、伊丹酒の澄み具合いを諸白と呼んで称えた。その昔、酒といえば、濁り酒(どぶろく)が当たり前だったのを伊丹で澄み酒(清酒)が開発され、いつしかそれが日本酒の主流を成した。清酒が生まれたのは伊丹の鴻池の地。戦国期に尼子再興を願った悲将・山中鹿之介が上月城で敗れ、その息子の幸元が叔父を頼って伊丹へ逃れた。やがて鴻池の地で酒蔵を興し、清酒を開発する。そんな歴史が伊丹酒には隠されている。江戸期には酒造りで伊丹郷は賑わっており、「摂津名所図絵」には60軒余りの造り酒屋があったとされている。この事でもわかるように伊丹は酒造の町なのだ。
そんな伊丹郷を代表する酒蔵といえば、清酒「白雪」でおなじみの小西酒造だろう。小西酒造は創業が天文19年(1550)と古い。伊丹で薬種業を行っていた小西家が江戸初期の慶長17年(1612)から清酒づくりを行い、以来今日までその伝統を守っている。「山は富士、酒は白雪」のフレーズは誰もが聞いた事があるだろう。二代目の小西宗宅が寛永12年(1635)に江戸へ向けて酒樽を馬の背に乗せて運んでいた折りに、ふと目にした富士山が美しく、雪をいただい気高い姿に感銘を受けて「白雪」と名づけた。いわば清酒「白雪」は、現存する最古の清酒銘柄と伝えられているのだ。




日本酒造りに邁進して来た小西酒造がクラフトビール造りに乗り出したのは平成7年(1995)の事。同社では、地ビールの規制緩和が行われた平成6年(1994)以前よりベルギービールの輸入・販売を手がけていた。規制緩和によって地ビールが造れるようになったためにベルギービールのノウハウを導入し、自社でクラフトビールを製造するようになった。
ベルギーから職人を呼んで、そこに日本酒造りの技術を加えながら「白雪ビール」を完成させたのである。「白雪ビール」を醸造するのは、「白雪ブルワリービレッジ長寿蔵」。つまり今回の話の舞台である「白雪ブルワリーレストラン長寿蔵」の中である。この場所は、かつて小西酒造の本社があった所。JR伊丹駅と阪急伊丹駅のほぼ中間で、東西に延びる、いわゆる酒蔵通りに面して建っている。「白雪ブルワリーレストラン長寿酒」(以降「長寿蔵」と表記する)の外観は、古くからある酒蔵然としたもの。それもそのはずで、昭和初期まで実際に酒造りを行っていた築250年ぐらいの酒蔵を改造して使っている。建物の二階には、酒造りの説明や道具を展示したブルワリーミュージアムがあってセミナーなど色んなイベントが開催されている。一階はブルワリーレストランで、ここにはクラフトビールの醸造設備も併設されているのだ。同店の店長を務める合志達矢さんの話では、「一階の店舗と二階の個室を合わせると約300名程収容します。伊丹市内でこれだけの規模でやっているレストランは、『長寿蔵』くらいなので使い勝手がいいのか、市民に愛されて来ました」との事。30年来ずっと通って来る顧客も多く、自慢の料理を食べながら清酒「白雪」と地ビール(白雪ビール)で一杯飲るために訪れるのが、ある意味伊丹の飲食シーンになっているという。ちなみに合志さんは、「長寿蔵」が出来た30年前からずっとここに勤めている。最早「長寿蔵」の生き辞引き的存在で、店の特性から顧客の嗜好まで全てわかあっているように思えた。実は「長寿蔵」は小西酒造が経営母体だが、その運営を飲食業専門の会社に委ねている。17年ぐらい前からは、万博などのイベントで食を提供したり、レストランのプロデュースなどを行ったりするフードサービス業の「初亀」が実際の運営を代行しており、合志さんは「初亀」の社員として「長寿蔵」で働いているのだ。
ビールといえば、かつては大手四社がほぼ独占状態で産していた。そこへ規制緩和が行われ、酒税法改正によって年間最低製造量が2000㎘から一気に60㎘まで引き下げられた。そんな緩和政策から地ビールと呼ばれるものが続々と産声を挙げるように。日本で地ビールが誕生したのは平成7年(1995)で、まさに小西酒造はその先駆けとしてクラフトビール造りを実施した事になる。「日本ではピルスナースタイルのビールが大半でしたが、ベルギーには約1000種と色んなタイプのものがあり、種類も豊富。スパイスなど何を入れてもビールと呼べるので表現方法は数多(あまた)あるわけです。ここでは無濾過(むろか)のエールタイプを醸しており、苦みも少ないのが特徴ですね」と合志さんが「白雪ビール」の説明をしてくれた。「長寿蔵」では、原材料にベルギー産の麦芽とホップを用い、清酒「白雪」に使用される地下水を仕込み水に使っている。そこに日本酒造りのエッセンスも加えており、米の糖化液をブレンドしているからだろう、飲んだ時に米の香が漂うように感じる。「長寿蔵」では、「KONISHIビールのテイスティングセット」があって「ゴールドエール」「ブラックエール」、ホワイトビール「スノーブロンシュ」と幕末のビールの復刻版「幸民麦酒」(日本で初めてビールを造った川本幸民にちなんで醸造)の四種(各100㎖)を飲み比べるようになっている。来店客はクラフトビールに舌鼓を打つのもよし、清酒「白雪」で料理を楽しむのもよしと、自由に食事シーンを楽しめる利点がある。
「長寿蔵」の料理に和の調味料を溶け込ませてみると・・・


さて肝心の料理の方だが、清酒「白雪」のアテになるようにと和食タイプも用意されてはいるものの、主はブルワリーレストランなのでビールに合う洋タイプが多い。合志さんによると、伊丹市とベルギーのハッセルト市が国際姉妹都市になっているらしく、クラフトビールはもとより料理にもベルギー色が反映されている。それを顕著に表したのが「ムール貝の蒸しナチュラル」「ムール貝のワイン蒸しガーリック」「ムール貝の香草パン粉焼き」といったムール貝の料理。ベルギーはムール貝の漁場である北海に面しているので昔からそれを好む。むしろ国民食といってもいいくらいだ。本場では白ワイン蒸しにビール蒸し、クリーム煮など色んなバリエーションが見られる。そんな背景も考慮して「長寿蔵」ではムール貝料理を売りにしている。合志さんが薦める「黒毛和牛のカルボナード」もベルギーを代表する一皿。牛肉をステーキのように焼いてからコクのあるビールで煮込んだもので、フランドル地方の郷土料理である。この地域は石炭産業で発達しており、石炭で鍋を加熱した事に由来する。ワインよりもビールが一般的らしく、煮込みにもビールが使われている。合志さんの話では「料理はオープン時から人気のあるものは残し、徐々に料理長の色を加えて替えて行った」そう。当初はやっていなかったステーキ類もその一つ。ビールに合うとの理由から数年前にメニューに加えた。「リブロースステーキやフィレステーキ、スペアリブは、五嶋料理長の意見もあって導入した料理。やはり肉料理としてわかりやすいのと、ボリュームもあるので人気です」との話だった。



昨今はコストカットなどの理由から飲食店での料理人不足が目立つ。でも「長寿蔵」は、歴としたシェフが存在し、レベルの高い料理を手作りしている。加えて専任のパティシエまで置いてデザート類の充実も図っている。
「長寿蔵」の厨房を司るのは、フレンチ出身の五嶋浩人さん。長年、ホテルニューオータニ系で調理して来た実績を有す人物だ。五嶋料理長はアルカイックホテル(現「都ホテル尼崎」)時代が長かったらしい。21歳から45歳までずっとホテルで勤め、「そろそろホテルの料理も卒業しないと」と思って「長寿蔵」に籍を移した。「長寿蔵」は純粋なフレンチではなく、街場のビアレストラン的な内容だが、「手作りが基本で精に合っているし、自分のペースでやらせてくれるのがいい」と言っていた。
そんな五嶋料理長が、今回の取材で湯浅醤油・丸新本家の商品に初めて触れて、その特性をいかした料理を本取材用に作ってくれた。一つは「タコのカルパッチョ」。この料理は、30年前から出している人気の品で、今回は「柚子梅つゆ」を用い、ソースを考えてくれている。「私が就任する以前からあるものは別段排除する理由はありません。少しずつ時代の流れを取り入れて考えながら残して行くからこそ30年も人気を保っているんですよ」と語っていた。本来はフレンチドレッシングで食べる所を今回はさらにもう一つ、「柚子梅つゆ」を用いたソースを加えている。「湯浅醤油の『柚子梅つゆ』は柚子や梅の味がいかされた調味料で、このままでもいいのですが、それだと芸がないのでオリーブ油で割って自分なりのアレンジを施しました。従来のフレンチドレッシングと共に供し、色んな味を楽しんでもらいたいですね」と話す。「柚子梅つゆ」にバージンオイルだけで割るのは強(きつ)かろうとピュアオイルも入れて味を調えている。こうする事で味が柔らかく感じるそうだ。一つずつのソースでタコのカルパッチョを味わい、最後は二つのソースを混ぜて食すのがいいらしい。



五嶋料理長が創作したもう一つは、「鯛のポアレ ブールブランソース」である。ブールブランは、仏料理で白ワインのバターソースをいう。仏語では白いバターの意味でワインと酢を煮詰めた中にバターを混ぜ合わせて作るのが一般的だ。鯛の表面をカリッと焼き上げ、ブロッコリーやパプリカなどを添え、仕上げにブールブランソースを掛ける。本来なら白ワイン・白ワインビネガー・エシャロット・バターで作る所に今回は醤油(「樽仕込み」)を加えて調味した。そして最後に軽くオリーブ油を掛けて出している。「今でこそ仏料理も軽くなっていますが、本来は味が濃いので、そこに醤油を用いたとて味は決まり易いんです。『樽仕込み』は、コクがあって塩味のトゲトゲしさがありません。口内にずっと余韻が残る味わいですね。当初は醤油を入れたらどうなのだろうと思っていましたが、うまく行きましたね。完成されたプレーンソースの味を邪魔する事もなく、うまくはまりました」と言う。料理人はその経験値から頭の中にレシピがあってすぐに再現できるという。だが、五嶋料理長は「成長するためには、他のものも加えて新たな味を模索するべき」と言ってアレンジを楽しんでいるかのような節があった。
だからだろう、この料理にもう一つのアレンジ版をすぐに作ってくれた。それはブールブランソースから醤油を抜いて、そこに味噌を加えたもの。新たに加えた味噌は丸新本家の「赤みそ」である。送って来ていた商品の中に「赤みそ」が入っていたので、それを使ったらどうなるかと突然試したくなったらしい。「赤みそはスタンダードな調味料なので我々料理人は色の具合いを見てすぐに味の構成が組み立てられるんですよ。時に納得できない味噌もありますが、これはそうではない。すぐに味が決まりましたね」と五嶋料理長。彼の話では、ブールブランソースに味噌を入れたのは今回が初めてだとか。その試みにご満悦気味で、五嶋料理長は「赤みそ」を用いたソースの方が気に入っている様子だった。醤油と味噌ではソースの重みも異なって来る。でもこのブールブランソースは、味噌を使っている分、まったりはしているが、そんなに重さもなく、まとまりがいい。五嶋料理長の言っている感覚が味わってみると、よくわかった。


三つ目の料理は、デザートで「カボチャのクリームブリュレ カカオ醤のオレンジソース」である。タイトルでもわかるようにここでは「カカオ醤(ペースト)」が使われている。この料理を創作したのは「長寿蔵」のデザート担当・井上満さんだ。彼はお菓子の道ばかりを歩んで来た。心斎橋にあった「ル・アイ」(伊料理店)で仏菓子のアトリエにいて、その後何軒かの仏菓子店を渡り歩き、7年前から「長寿蔵」でデザートづくりを任されている。ここでは酒蔵のレストランらしく「日本酒テリーヌ」や「酒粕チーズケーキ」「SAKEティラミス」が彼の作品で人気があるらしい。「奈良漬けソフトクリーム」を少し合志さんからいただいたが、奈良漬の味噌を使って作っているらしく、口に入れただけで奈良漬の風味が漂う。合志さんによると「好きな人は、奈良漬を刻んで入れて」と注文するそうだ。ちなみにこの品は、現在開催中の大阪・関西万博の「醗酵食堂Hasshoku」で供されており、結構人気なのだとか。
本取材用に井上さんが作った「カボチャのクレームブリュレ」は、まずカボチャを70℃の鍋の中で弱めに叩いて粗めに潰し、それからオーブンで蒸し焼きに。冷ましてから上白糖を振り掛けてバナーで炙ってキャラメル状にする。そこに「カカオ醤」で作ったソースを掛けて仕上げるのだ。このカカオ醤ソースは、オレンジジュースで延ばし、ひと煮立ちさせてバターでコクや照り、とろみをつけて作っている。井上さんは、「水で延ばすと醤とわかるようなのでほんの少量のオレンジジュースを代用させ、フルーツの風味で下支えにしました」と説明していた。
この一皿が出て来ると、ほんのり醤油香が漂っていた。これが「カカオ醤」ソースの効力なのだろう。井上さんは、発酵食品の掛け合わせをテーマに創作したそう。チョコレートにオレンジは、好相性。それらにカボチャも合う事からカボチャのクレームブリュレを選んだ。「甘くないのにチョコレートの雰囲気を出しているのが『カカオ醤』の面白い点。カカオニブをかじると、この手の味がするんですよ。この調味料は醤とカカオが共存してどっちが勝つわけでもありません。味わうとまずカカオ風味が来て醤がその後から追い駆けて来ます。生地に練り込んでしまうとその味しかしなくなりそうなので、あえて掛けて完成させる手法を取ったんです」と教えてくれた。

今回は、「名料理、かく語りき」用に取材の際に私だけのスペシャリテを披露してくれたが、このような発想の面白さから五嶋さんや井上さんがメニューづくりを行なっているのがわかってもらえたと思う。全般的に「長寿蔵」の料理は、一皿の量が多く、シェアしながら食べるのがいいのかもしれない。夜は3200〜3300円ぐらいあれば楽しめるそうで、宴会用は5500〜6000円飲み放題込みで提供しているという。結構リーズナブルなのに、ボリューミーさがウケているのだろう。五嶋料理長は、その理由を「手作りする事でコストが落ちるからだ」と言う。コストカットを理由に冷凍食品や出来あいものを仕入れて出す今の風潮に一石を投じる発言だと胸を打たれた。レストランはそうでなければならない!なぜなら平たく表現すれば、料理屋なのだから…。合志さんは「30年前にあったメニューをリクエストして来る顧客もいます」と言う。「やれる事はやりなさい」と言うのが経営者のモットーで、五嶋料理長も「食材があれば作りますよ」と言い放つ。何とも小気味よい発言で、サービス業とは何たるものかを教えてもらった気がする。
-
<取材協力>
白雪ブルワリーレストラン長寿蔵
住所/伊丹市中央3-6-15
TEL/072-773-1323
HP/ 公式HPはこちら
営業時間/11:30〜21:00
休み/火曜日
メニューor料金/
ムール貝のワイン蒸しナチュラル(S)1200円、(M)1850円
ムール貝の香草パン粉焼き 1200円
黒毛和牛のカルボナード 1850円
秘伝の唐揚げ 880円、(大)1700円
長寿蔵特製アンチョビポテト 650円
厳選リブロースステーキ(250g)2780円
豪快スペアリブ(ビーフ)2750円
ソーセージ盛り合わせ 1730円
絶品グリル盛り合わせ 2280円
サーロインローストビーフ 1700円
白雪酒粕ピザ 1360円
柴漬けピラフ (フル)1050円
白雪の奈良漬けと漬物盛合せ 600円
鯖の炙り寿司 1480円
日本酒テリーヌショコラ 680円
酒粕チーズケーキ 630円
※価格は全て税込み表示
筆者紹介/曽我和弘
廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。