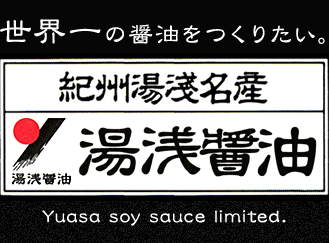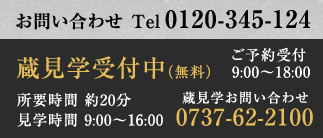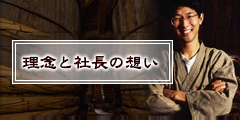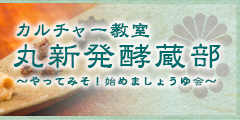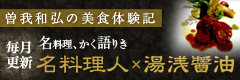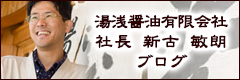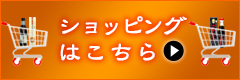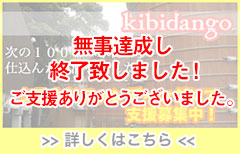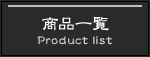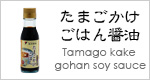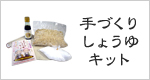141
水茄子は、泉州地区の特産品。中でも泉佐野市内で多く生産されており、市の農林水産課では“泉佐野産(もん)”と銘打ってブランド化に勤しんでいる。水茄子といえば、食べ方は生か、浅漬けと相場は決まっているのだが、私は更に調理汎用の良さに着目している。「一般的な茄子でできる料理ならば、水茄子でも可能」とシェフ達は声を揃えて言うように、天ぷらだって麻婆茄子だって水茄子でできる。いや、むしろ長茄子より旨いのだからびっくりする!今回は、そんな私の活動を示すかのように大谷直也料理長が「さかばやし」の旬の会で、水茄子づくしの会席料理を提供した話をレポートしたい。水茄子の特性をうまく使って先付から甘味(デザート)までの八品にいかに驚きを持たせたかを書く事にする。
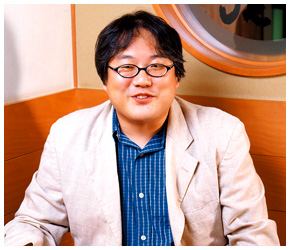
- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。
水茄子会席でお目見得した水茄子料理の数々


6月にユニークな食事会が開かれた。神戸酒心館「さかばやし」で催された「採れたての水茄子の旬菜料理と初夏の生酒を楽しむ会」がそれ。この食事会は、「さかばやし」がその時季時季のいい素材をテーマに企画する“旬の会”の一環。今回は泉佐野市農林水産課とコラボして行うもので、泉佐野の水茄子農家・辻裕男さんから直送されたもぎたての水茄子を使って大谷直也料理長が料理を提供するイベントだ。そう書くと「どこがユニークなの?」と突っ込まれそうな気がするが、実はその献立の内容にユニークさが隠れている。
そもそも水茄子は、泉州地区で獲れる特産物。その発祥は、日根野の澤村(貝塚)とも上之郷村(泉佐野)とも伝えられている。室町期の「庭訓往来」には、澤茄子と書いて「みつなす」と読む記述が見られ、多分それが水茄子の文献初出ではないかと思われる。江戸期には本格栽培が行われていたそうだが、果物に近い扱いだったという。水茄子が関西全般で知られるようになったのはバブル期くらいから。TVで水茄子を生で丸かじりするシーンが放じられ、「茄子なのに生で食べるの?」と話題になった事による。JA大阪泉州で生産出荷協議会の会長を務めていた辻裕男さん(泉佐野の水茄子農家)に聞くと、「茄子は全国で約200種もあるのですが、その中で生で食せるのは、泉州の水茄子や新潟の十全茄子とほんの少しだけ。それくらい泉州の水茄子は珍しい種類のものなんです」と_。最近は千葉や高知・徳島でも水茄子を栽培しているが、泉佐野在住の消費者は「売っているものを買って糖漬けにしてもうまく乳酸発酵しなかった記憶があります。印象としては顔が瓜二つでも別物という感じですね」と話していた。やはり水茄子は泉州の土と気候が生んだ産物なのであろう。







水茄子といえば、生か、浅漬けとその用途は決まっている。元来、茄子は灰汁が多く生食に向かないとされているが、水茄子は灰汁が少なく、皮も薄く、果肉も柔らかいので生食需要(もしくは浅漬けに活用)が一般的だ。余りにその2パターンに相場が決まりすぎているために天邪鬼な私は調理汎用を薦めたくなってしまった。シェフ達を巻き込んでその検証をしてみると、水茄子が調理素材に向いている事が徐々にわかって来た。例えば天ぷら_、長茄子の天ぷらは当り前だが、いくら美味しくとも油を吸いすぎて重くなってしまう嫌いがある。ところが水茄子を天ぷらにすると、茄子自体に水分が多く含まれるために油を吸いすぎず、あっさりと食せるのだ。逆にだしに浸けると、うまくだしを摂り込んで美味しくなる。「紅宝石」(神戸・元町)の李順華シェフにいわせると、「麻婆茄子はむしろ長茄子で作るより水茄子の方が旨く仕上がる」らしい。そこで泉佐野市農林水産課と一緒に水茄子の調理汎用性を訴求する事にした。水茄子はその特性上、夏のものと決まっている。夏場の出荷が当たり前だろうが、その産地として名を馳す泉佐野市では夏以外でもハウス栽培でそれを作っている。ならば調理汎用性の良さを訴えれば、寒の時期でも温かい料理に使えるので、需要の幅は拡大するのではないか。泉佐野市農林水産課では、泉佐野産(もん)商品化プロジェクトと題して令和5年度と6年度に延べ10人の料理人がその検証を行ってレシピを寄せている。そんな中の一人が「さかばやし」の大谷直也料理長。彼は6月の会席料理の献立にも泉佐野産の水茄子を用いたりしながら水茄子料理を推進しており、泉佐野産商品化プロジェクトで提出したレシピのうち、「水茄子蕎麦」はすでに昨夏にメニュー化。ありそうでなかったこのメニューが好評で、昨年の夏はかなり出たと言っていた。
さて6月10日に催された「採れたての水茄子の旬菜料理と初夏の生酒を楽しむ会」では、“水茄子の会席料理”と称されるだけあってうまく調理汎用性を示した一品一品が提供されていた。ちなみにその献立を列挙すると下記の順に_。
先付/水茄子の白衣和え
新じゃが芋、赤茄子、アスパラ
吸物/清汁仕立て 鱸葛打ち
翡翠水茄子、尊菜、新蓮根、椎茸
造り/生水茄子と鮮度二種盛り
間八、太刀魚、あしらい
合肴/水茄子昆布締めと黒毛和牛ロース煮
水茄子ガスパチョを添えて
箸休/冷製茶碗蒸し
水茄子、浅利、銀餡、山葵
強肴/水茄子の酒粕グラタン
神戸ポークベーコン、ズッキーニ、丹波婦木農場熟成ラクレットチーズ
食事替/自家製水茄子蕎麦
甘味/水茄子コンポート、福寿酒粕アイス
大谷料理長は、泉佐野産(もん)商品化プロジェクトにも参加しているだけあって水茄子料理に関してはかなり研究を積んでいる。6月は「さかばやし」の季節のミニ会席、灘会席、酒心館会席にもかなり多くの水茄子料理を登場させているが、それとは別に旬の会では水茄子の特性を上手く使った料理を提供していて実に面白い献立になっていた。「この日の会席料理は、水茄子づくし」と私も宣言して神戸メリケンパークオリエンタルホテルの鍬先章太シェフらを客として誘っていたが、同業者に対する挑戦的な思いもあったのか、先付から甘味まですべてに泉佐野産水茄子を用いて調理していたのである。事前に「吸物とご飯以外は全て水茄子料理」と触れ込んでいたが、蓋を開けてみるとびっくり。吸物にも翡翠水茄子が入っているし、食事は昨夏評判を得た水茄子蕎麦にしているしで、「そう来たか!」と参加者を驚かせていた。献立の中で好評を博していたのが「水茄子の酒粕グラタン」。福寿の酒粕と婦木農場の熟成ラクレットチーズで酒香漂うグラタンに仕上げ、中には水茄子が入っていた。大谷料理長の話では、長茄子だと柔らかさが出ないそうで、水茄子を入れて熱する事でとろっとした果肉の良さが伝わるのだとか。流石に酒蔵の料理屋だけに酒粕をうまく使った一品に仕上げていた。「水茄子昆布締めと黒毛和牛ロース煮」も印象に残った一つ。文字通り水茄子を昆布で締め、牛肉と一緒に並べてジュレを掛けている。添えられたガスパチョが秀逸で、ここにも水茄子が使われていた。ガスパチョはスペインやポルトガルに見られる冷製スープで、トマトを用いるのが一般的。大谷料理長はそこに水茄子を加えてミキサーで攪拌している。酸味が利いてまさに夏向きである。甘味の「水茄子コンポート」は、開催ぎりぎりまで構想を練っていた品らしい。以前、泉佐野産(もん)商品化プロジェクトに参加していた「ホテル日航関西空港」の井口晃一総料理長が生の水茄子はフルーツに通じるものがあると話していたが、このコンポートはその通り。コンポートとは、果物を水や薄い砂糖水で煮て作るお菓子だが、水茄子を用いるとリンゴのコンポートのような雰囲気に。水茄子なので甘さはそこまでなく丁度いい塩梅(あんばい)の甘みになっている。添えられた酒粕アイスクリームと一緒に食べると、さらに旨みは倍増するらしく、参加していたご婦人方が「一緒に味わうと旨い!旨い!」と絶賛していた。プロ的目線でいえば、水茄子の白和えが実に合う事がわかった。白和えは豆腐や白ごま、白味噌で和える料理で、食材が白い衣をまとっているように見える事から“白衣和え”と称される。この料理は、豆腐などと合わせるから味の主張がほどほどの食材がいいのかもしれない。そういう意味では、水茄子はぴったりの素材ではなかろうか。大谷料理長も「作ってみてこんなに合うとは思わなかった」と話していた。造りはカンパチと太刀魚が出ていたが、ここに生の水茄子を添えると、造りのいいあしらいになる。生の水茄子をうまく味あわせる工夫の一端が見られて面白かった。
たった1%ほどの水分量の差なのに、なぜ瑞々しい?!






たまたま一週間前に今回の水茄子を送って来ている辻裕男さんの畑に見学に行って来た。辻さんは代々の泉佐野農家だが、若い頃は農業を継がず料理人になっていた経験もある。一時期は飲食店もやっていたが、とどのつまり農家に戻って水茄子を作っている。だから他の農家より料理への関心も強く、水茄子の用い方もよく知っている。「それでもサラダに生で使ったりする以外は考える術はなく、こんな風に色んな料理に向く事がわかって面白かった」と食事会では席上で感想を述べていた。水茄子を多く産する泉佐野の農家でも辻さんは少し特殊で、一部の月の除いて一年中水茄子を栽培しているそう。「4月初旬から6月末まではハウスで促成栽培をし、7月から8月末までは露地栽培を行います。11月~12月がハウスにて超促成栽培を実施し、それを冬のギフト用に回しています」と話していた。水茄子は、出荷時にA・B・C・外とランク付けされるのだが、まさに形の良さが重要ポイントで、大きさは2L・L・Mサイズに分けられる。Bは多少ゆがみがあるもので、CはBよりゆがんでいたりしてランクが一番落ちるレベル。それより下の外ランクは、穴があったり、艶がなかったりして見た目が悪いものを指す。皮も硬く、皮が割れたりしたら外ランクにも通らず、直売所で安く叩かれて売ってるか、捨てるしか手はないらしい。そういえば、ビニールハウスの前にいくつか干からびた水茄子が転がっていたが、それが外ランク外にあたるのだろう。辻さん宅でサラダに使用した例と糖漬けしたものを味あわせてもらった。流石は元料理人らしくサラダもうまく使っており、ドレッシングはお手製だという。糖漬けにしたものが秀逸で、漬物にしているが、生の雰囲気を保たせており、市販の味とは少し違っていた。辻さんは、夏場がかき入れ時で忙しいから自らは漬物を漬けないらしい。繁忙期を過ぎてギフト用を出荷する11~12月に漬けたものを出していると聞く。辻さんが出して来た漬物は「この辺りの農家や家庭が作るやり方で漬けている」との事。「いい水茄子は果肉が柔らかく、乳酸発酵します。半日漬けるだけでいいんですよ」と言う。「茄子のお尻部に艶がないものは、ボケ茄子と呼んで外ランクに落ちるんです」と_。水茄子栽培は手入れが大変で、毎日剪定しないといけないようだ。辻さん曰く「盆栽のように剪定するのがひと仕事だ」とか。
水茄子は読んで字の如く水分を多く含み、瑞々しいからそう呼んでいる。ところが、水分量を計るとあながち一般的な茄子を大差がないようだ。某調査では、水茄子が95.2%の水分量があったのに対し、千両二号という一般的な茄子は94%。わずか1%程の差しかないのだ。辻さんは、ボウルの上で一般的な茄子を力まかせに搾っていたが、一滴も水が出なかった。でも水茄子だと手で搾ると、ボタボタと水が滴り落ちる。つまり含有水分量は大差なくとも弱い力で果肉から果汁がどっと出て来るという証明に。これこそが水茄子たる所以で、果肉のジューシーさを示すものである。瑞々しいとは、この事で、かつて農家の人が畑で水分補給のために水茄子を搾って飲んでいたとの話がよくわかる。6月の会席料理や「採れたての水茄子の旬菜料理と初夏の生酒を楽しむ会」は終わってしまったが、「さかばやし」では、好評の「水茄子蕎麦」は夏期の間提供しているそうだ。このレポートを読むだけではつまらないという向きは、ぜひとも「さかばやし」まで足を運んで「水茄子蕎麦」を味わって欲しい。