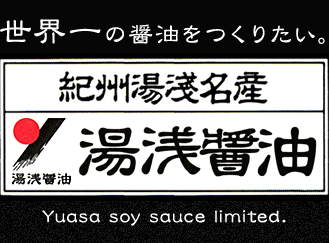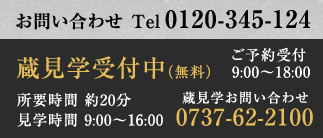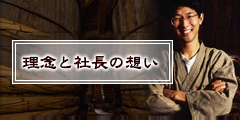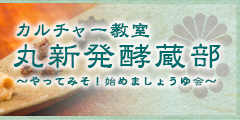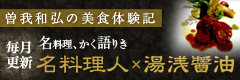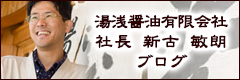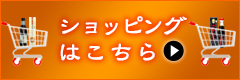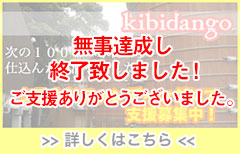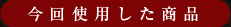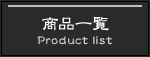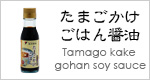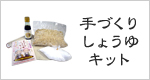139 2025年05月大阪に「万両」なる焼肉店がある。南森町店を皮切りに大阪の街中に都合6店舗あり、焼肉通の間では高い評価を得ている。一時は「食べログ」で大阪の焼肉店で一位に輝いた事もあるとかで、私の周りにもそのファンがいて通っているとの話も耳にする。この「万両」が実は数年前から湯浅醤油の「樽仕込み」を使っているそうで、一般的な焼肉のタレではなく、「特選ロース」など霜降り度が強い肉を焼いてダイレクトに醤油に漬けて味わうメニューをいくつか用意しているのだとか。ならば一度取材したいと久しぶりに「万両」南森町店を覗いてみた。そこで店主・滝本昭人さんに聞いた「万両」のここまでの道のりと共にレポートしたい。
万両 南森町店 滝本昭人
(「万両」オーナーシェフ)
 「いい醤油を用いると、
「いい醤油を用いると、
自ずと肉の評価も上がります。
湯浅醤油の商品は熟成度も高く、
旨みが凄い。
なのでダイレクトに漬けて楽しむ商品をいくつか用意しました」
上質肉をダイレクトに漬けて相乗効果を狙いたい



「焼肉の『万両』って知っているでしょ」_、いきなり電話口で新古敏朗さんが焼肉店の話をし出した。「万両」は、“席に待ったあり!味に待ったなし!”のキャッチコピーを掲げる大阪の焼肉店で、創業してすでに30年以上になる。かなり昔に私も南森町店で食事をした経験があったが、今では本店を皮切りに天神橋店、東天満店、肥後橋店、本町御堂筋店、日本橋店と都合6店舗を有す老舗格になっているようだ。新古敏朗さんが言うには、何でも「万両」のオーナー・滝本昭人さんと知己を得て以来、湯浅醤油の「樽仕込み」を仕入れて店で使ってくれているとか。新古敏朗さんが滝本さんと会ったのは、どうやらコルトレーン研究家の藤岡靖洋さんを介してらしい。藤岡さんは、グルメらを集めて毎年、「鯛よし百番」で「正しいすき焼きの作り方会」を開いている(第128回名料理、かく語りきを参照)。その会で二人が知り合い、意気投合して仕入れにまで繋がったようで、滝本さんも「その時に醤油の話を色々と聞かせてもらった」と言っていた。以降、滝本さんは湯浅醬油の商品群に惚れ込み、自身の店(「万両」)でも使うようになったようだ。新古敏朗さん曰く「なので『名料理かく語りき』の取材にどうですか?」との推薦である。そんないきさつから久しぶりに「万両」南森町店を覗くに至った。同店は、大阪メトロ・南森町駅から程近く、天神橋筋商店街より西の阪神高速高架の手前に位置している。私が昔訪れたのもこの店で、どうやらその頃より広くなっていて継ぎ足しながら店を拡張したようだ。
滝本さんの話では、33年前に「万両」はカウンターのみの8席の焼肉店からスタートしたそう。モツ鍋ブーム乗って11席に増やし、その後隣りも借りて今の陣容になっている。「万両」は、七輪に炭をいこして肉を焼くタイプの店で、その臨場感も相俟って焼肉屋らしい趣がある。こだわりは当然ながら肉の質にある。殊、仕入れにはかなりこだわっているらしく、HPには「厳選、一頭買いをしているので定番のロースやカルビの他に、他店ではなかなか見かけない希少部位が楽しめるのも人気の秘密」と記されているのだ。特にモモ肉の中でもヒウチと呼ばれる部位を使用しているのは売りの一つで、説明では一頭から3kgしか採れない希少部位らしい。この部位は数量限定の売り切れ御免の商品で、片焼き30秒でネギをたっぷり包んで食すのがオススメのよう。「コテツ」と呼ばれるホルモンは南森町店限定の部位。コテツとは小腸にあるホルモンで、テッチャンよりも皮が薄く、脂が多い。ホルモン独特の硬さと味があって少ししつこさを有す。滝本さん曰く「昔はホルモンといえばコテツ。今ではテッチャンに代わってしまったが、再度ブームが訪れている」との話で、「万両」南森町店では、コテツの一本焼きが人気があるそうだ。


さてそんな「万両」では、定番焼肉のタレには湯浅醤油の商品は使用せず、「サーロインロースの角切り」や「特選上ロース」「塩レバー焼き」に「樽仕込み」を用い、辛子醤油や生姜醤油に漬けて食べるようにして提供している。その他の造り系も同じで、「生タンのお造り」や「生ツラミ刺し」を頼んでも「樽仕込み」が添えられて出て来るのだ。滝本さんは「いい醤油があれば使いたい」と常々思っていた。藤岡さんの「正しいすき焼きの作り方会」では、湯浅醤油の「生一本黒豆」が使われており、その時に初めて味わった滝本さんは「旨みが凄い」と実感したという。「塩味があるのに決して辛くない。まろやかなのに旨みもあって惚れ込んでしまいました」と語っていた。ならば色んなものを混ぜて作る焼肉のタレではなく、ダイレクトに漬けて食べる方がいいと思って上記のメニューに添えるようにしたそう。当初はそれをインターネット販売で注文して活用していたらしいが、湯浅醤油の北山さんに相談したところ、安定供給という点でも、業務用卸しという点でも「樽仕込み」の方が「万両」に向いているとの事で、今ではその業務用を仕入れて全店で活用しているとの話であった。「万両」がなぜ旨い醤油にこだわるのかというと、滝本さんは「醤油単体で味がわかる人は少ないと思うんです。でも『樽仕込み』に漬けて味わうと、万人が肉が旨い!との結論になる。そんな相乗効果を期待しているんですよ」と本音をポロリと漏らしてくれた。だから「仕入れ値段が高くても使うべき」と断言していた。「樽仕込み」は、辛子や生姜といった薬味との相性も抜群で、それらの肉には辛子醤油や生姜醤油で味わうように薦めている。全てはいい肉を味わうための設計図になっているのだろう。




私も取材用にと「サーロインロース角切り」や「特選ロース」を辛子醤油で味わったが、肉の良さが感じられ、口内にそのジューシーさが伝わって行き、尚更醤油がいい役目を果たすように思える。そして肉の柔らかくて適度な脂が幸せな気分に浸してくれるのだ。まさにダイレクトに辛子醤油に漬けてもうまく太刀打ちしている。肉も醤油も負けていないのがわかる。「塩レバー焼き」は、きれいなレバーが出ていた。まるで生ででも食せると見紛うようなレベルの品である。ゴマ油の上にレバーが載せられ、横には生姜と塩が添えられている。このレバーを七輪で焼いて食べるわけだが、塩で味わってもいいし、生姜醤油に漬けてもいいしで、味変も楽しめるようになっている。勿論、私は生姜醤油を選択した。
滝本さんは、ご飯と焼肉がそもそもの原点で、この二つを一緒に食すと若い頃を思い出すと言っていた。「万両」では、焼肉に合うようにと、特別にブレンドした米でご飯を炊いている。米は京都の老舗米屋「八代目儀兵衛」から仕入れている。「八代目儀兵衛」は、米を1%刻みでブレンドする事で知られており、シングルオリジンでは感じる事のできない奥行きのある甘みを引き出す。そんな米を「万両」では、ロボット化したもので炊いて出す。「自動米研ぎ機と自動米つぎ機と合体したような炊飯器を導入して研ぎ、炊き、つぎの心配を従業員がしなくていいように設置したんです。蓋を一回閉めるだけでよくて、柔らかくホワホワした、ほどけるほど豊かなご飯の味わいがこの一台で実現するんです」と説明していた。焼肉とご飯がうまくマッチしているからだろう、醤油に漬けた肉をご飯にワンパンするようにして味わうと、肉の旨みをまとった醤油が白ご飯について、最近TVで話題のワンパンライスを演出していた。滝本さんは、焼肉を美味しく食してもらうには脇役が大事で、これらが揃ってこそ満足度の高い焼肉店が完成すると話していた。肝心の肉だけでなく、色んな所にこだわりが見られるからこそ「万両」は焼肉通に支持されているのだと実感した。
時代の流れに乗って「万両」も躍進


ところで新古敏朗さんが私に「万両」の取材を薦めたのは、滝本さんの話の面白さをしってもらいたかった事にも一因がある。「万両」は今でこそ大阪の有名焼肉店だが、そのスタートは凄まじい。滝本さんが「万両」を始めたのは33年前で25歳とまだまだ若手の時代である。彼は焼肉店・焼鳥屋・居酒屋とずっと飲食業界の道を歩んで来た。25歳の頃に当時勤めていた店のオーナーから「焼肉屋をやらないか」と誘いを受けた。南森町にあった「万両」という店が調子が悪く閉店に追い込まれていたからだ。「万両」の前店主と滝本さんが働いていた店のオーナーが知り合いで、借金付きで引き取り手がないかと相談していたようだった。そこで滝本さんにお鉢が回って来たのだとか。勧めてくれたオーナーからも「いずれ独立するなら」と背中を押され、25歳という若さで自分の店を持つに至っている。「ゼロからのスタートではなく、借金付きで『万両』を引き取ったのでマイナスからのスタートだったわけです。焼肉屋なら内装はそのまま使えそうだし、仕入れ先も紹介してくれるとの話だったので好きにやらせてくれるならとの条件で思い切って自店を持つ事にしたんです。若いし、持っている財産も何もないから失敗してもいいかとの気持ちでスタートしたんですよ」と当時を振り返ってくれた。
赤字続きの不振店だったので当初は暇だったそうだ。滝本さんのお母さんも手伝ってくれて焼肉屋といえど、おでんやだし巻きも出したりと、毎日来店してもらえるようなメニュー組みをしながら1992年10月に「万両」を開いている。
転機となったのは翌年の秋_、モツ鍋が一大ブームとなる。モツ鍋自体は戦後まもない頃から大阪にもあったみたいだが(発祥は博多との説がある)、どちらかというとマイナーな存在で労働者が食べるものとのイメージだった。それが1992年に東京に博多風モツ鍋店がオープンすると、安くてボリュームもあって酒に合うと大ブレイク。バブル崩壊後の風潮とも合わさって新語・流行語大賞に選ばれる(銅賞)ほどのブームになってしまった。その波が大阪まで来て、色んな所でモツ鍋屋がオープン。挙句の果ては「モツが足らない、ニラが足らない」という材料不足までに発展した。「万両」は焼肉店なので内臓肉の仕入れには困っていなかったので「ならばうちでもメニュー化しよう」とモツ鍋を売り出すことに。「今から思えば恥ずかしいくらいのレシピだった」と振り返るが、味噌味スープのモツ鍋はとりあえず評判に。「焼肉屋のモツ鍋」と手書きで貼り出したのもあって一見客がどっと押し寄せたという。「うちの内臓肉が旨いのは当然。その辺のモツ鍋屋と違ってうちは和牛のモツを使っているのだから差別化できるわけです。他店は二人前からの注文だったので『万両』では一人前から頼めるようにし、食べ易くしました」と滝本さん。あまりの人気ぶりに8席だった店を改装して11席に増やして営業した。これで「万両」の経営が軌道に乗り始めた。



ただブームとは一過性のもので、飽きが来るとすぐに終息してしまう。カウンターで仕事をしていると、食べている人もブーム時みたいに美味しそうな雰囲気を醸し出していない。滝本さんは、いっその事、モツ鍋をメニューから外し、焼肉一本で勝負しようかと考えた。もとの焼肉店に戻すと、モツ鍋目当てで来店した顧客から「せっかく訪れたので仕方がないので焼肉を食べるわ」との声も聞かれた。「モツを焼いたら、『旨いなぁ』と言ってくれ、いい肉を出していれば徐々にそちらにニーズが向くようになって行きました」と言う。そうこうしているうちに“黒船”がやって来た。そう「関西ウォーカー」(角川書店)の発刊である。それまで関西には「ぴあ」や「京阪神エルマガジン」などの情報誌はあったが、東京から来た「関西ウォーカー」は、これまでのデータの羅列の編集を覆し、テーマごとに店を選出。数多くを載せるのではなく、どこかにスポットを当てる事で誌面を充実させた。時期を同じくして「牛角」の関西初出店が関目にオープン。この頃から焼肉屋がカップル仕様になったり、デートに使うようになったりとガラリと一変して行く。関西ウォーカー編集部も「万両」の評判を耳にし、「下町の焼肉特集をやるんですが、ぜひ取材させてもらえませんか?」と依頼して来たのである。そして7月に「関西ウォーカー」の誌面を「万両」の記事が飾った。すると行列ができるほどに。開店前には、すでに並んでいてオープンと同時に席が埋まる_、そんな日々が続いたという。1992年には、「関西ウォーカー」人気に追随すべく講談社が「KANSAI1週間」を創刊。旧来の「ぴあ関西版」や「SAVVY」などと入り乱れてグルメ情報過多の時代へと突入。それまで焼肉屋というと、男性客のイメージで、ガッツリ食べるのを目的に行く場所だったのが、デートの場として活用されるようになってその印象は一変した。関西の雑誌戦争が焼肉ブームを巻き起こし、それによって「万両」もブレイクしたのである。




滝本さんは、三段飛びにたとえるならモツ鍋ブームがhopなら、情報誌ブームがstepで、jumpはSNS時代だと表現する。2001年の狂牛病問題で一時期大きなダメージを受けた焼肉業界もSNSの普及によって復活を遂げる。「食べログが流行し、潮目が変わった」とまで言い、口コミ情報によって遠方からの顧客も拾えるようになったのである。以前なら天神橋筋商店街からの流れや周辺の法曹界からの常連客が主だったのを、SNSによって吹田や八尾からも来るように。「うまいもんを食べるなら少々足を延ばしてもいいとの風潮が占め、『食べログ』で高評価の店を探して訪れるようになりました。SNSによって顧客の流れが変わったんですよ」。気づいたら「万両」が大阪の焼肉店では1位の座に。ネット時代の到来は、まさに「万両」の追い風となって評判を高めたのである。
風に乗ったのも要因ながら、いい肉を出していないと飽きられてしまう。「万両」は滝本さん自身が仕入れにこだわり、飽きささぬよう色んな戦術を駆使しているからこそ、今でも人気店の座を守っている。滝本さん自身、「万両」を経営するにあたって色んな戦法を試しながら常に顧客の満足度を高めている。いい醤油(樽仕込み)を使ってメニューごとに味わい方の差を出しているのもその一つだろう。ステーキ風の「サーロインロースの角切り」や「特選上ロース」のように脂の旨さが伝わる品は、「樽仕込み」でさっぱりさせる。醤油の濃さが霜降り具合にマッチしている。「生タンのお造り」や「生ツラミ刺し」といったいわゆる生ものは、一般的な(魚の)造りと同じようにダイレクトに漬ける醤油の役目が重要になり、旨みをいかすために用いている。それを滝本さんは「漬けて食べる事を強みにしたい」と考えており、湯浅醤油のような熟成度の高いもので、「いい肉を味わった」との演出を図ろうと狙っている。
滝本さんによると、「今はいかに野菜と一緒に味わってもらうかが課題だ」そう。元来、焼肉店ではロース、カルビ、タンといったように単品で注文する事が多い。野菜もあるが、チシャ菜や生ゴマの葉という具合に単品売りになっている。顧客も肉ばかりではなく、チシャ菜で巻いたりすると健康的でいいとわかってはいてもなかなかその通りオーダーが通るのは少ない。ならば初めからセット売りしてメニュー表に載せていればどうだろう。客側もその組合せを楽しんでくれるのではなかろうか。滝本さんが見せてくれた写真は、蓮根にロースが載ったものだった。「蓮根に同じ大きさのロース芯を載せて提供します。肉を焼いてから蓮根の上に載せ、燻すようにしてから下の蓮根も火を入れて行きます。蓮根は穴が開いているから自ずと肉も燻されるんですよ。肉を食べ終わったら、蓮根を厨房でカットして出します。これなら野菜も一緒に摂れると思いませんか?」。これからは、A5クラスの霜降り肉をこのようにして売って行きたいと話していた。売るためには店側も何らかの工夫が必要。努力せずに売れる時代は終わったのだ。滝本さんのサクセスストーリーとアイデアの豊富さを聞いていると、「万両」が人気店になった理由がわかって来た。Roma wasn’t built in a day_、和訳すると「ローマは一日にして成らず」となる。立派な事業は、長い年月をかけて初めて完成するの意で、大半の言語ではローマと称しているが、仏語ではそれがパリになり、エスペラント語ではカタルゴになる。ならば大阪の焼肉店では、そこが「万両」になるというのは、ちょっと持ち上げ過ぎだろうか(笑)。
-
<取材協力>
万両 南森町店
住所/大阪市北区天神橋2-2-14 ロイヤルハイツ1階
TEL/06-6356-5611
HP/ 公式HPはこちら
営業時間/16:00~24:00
休み/日曜日
メニューor料金/
生タンのお造り 900円
生ツラミ刺し 700円
サーロインロース角切り 1100円
特選上ロース 1550円
塩上レバー焼き 680円
厚切り特上塩タン 1680円
特選上バラ 1550円
クラシタ上ロース 1150円
アカセン焼き 600円
テッチャン 600円
ハチコリ 600円
コテツ一本焼き 550円
ご飯 小300円 中350円 大450円
ゴマの葉おにぎり 550円
※価格は全て税別表示
筆者紹介/曽我和弘
廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。