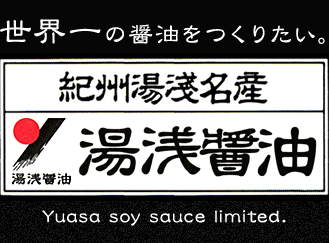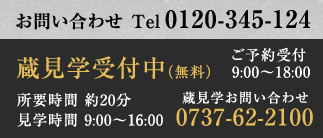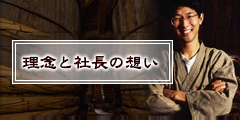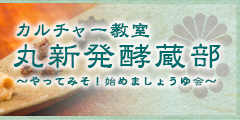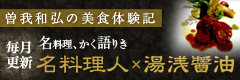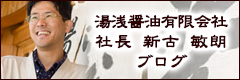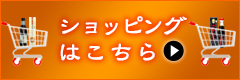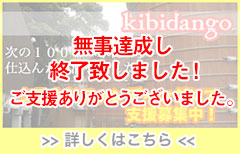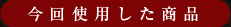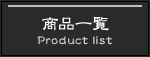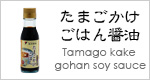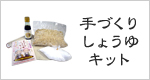142 2025年08月飲食店の紹介で、隠れ家とか、止まり木といった表現をよくする。隠れ家とは、人目を避けるための場所の意で、飲食店ではわかりづらい場所や他人に教えたくない店を指す事が多い。片や止まり木は、小鳥が休息などに用いる木の意で、バーなどの表現に用いるのがよくある。今回紹介する「舟櫓」(ふなやぐら)は、三宮・東門街の賑やかな場所にあってその二つともの表現が相応しい割烹ではなかろうか。東門街本通りの路地に佇む店を覗くと、まずカウンター前の鉢の多さに驚かされ、国産野菜を用いたおばんざいの数々に心を踊らされる。ここでは、それらのおばんざいをいくつか注文し、造りや一品料理を待ちながら一杯飲るスタイルが定着している。今回はそんな気軽な雰囲気漂う割烹でいつものアレをやりたくなってしまった。さて「舟櫓」を営む安藤夫妻は、いかに湯浅醤油・丸新本家の商品を一品料理に落とし込んだのであろうか。
舟櫓 安藤伸二郎・安藤喜子
(「舟櫓」店主)
 「赤だしは優しい味わいで、
「赤だしは優しい味わいで、
関西風料理に合います。
私自身も好みの味で口に合いました。
マイルドさがいいですね」
カウンター前のおばんざいの充実ぶりにびっくり




三宮・東門街_、正式には生田東門商店街というらしいが、生田神社すぐ東のネオン街なので〝東門街″の名で通っている。少し古い話になるが、このストリートは競馬場のコースに当たる。明治元年(1968)のクリスマスに居留地の北東部(今の市役所辺り)の砂利道で外国人達によって競馬が行われ、翌年には生田神社東の、今でいう東門街に競馬場が造られた。その様子を長谷川小信が「摂津神戸西洋人馬駆之図」に描いている。市街地の拡大や借地料の問題で競馬場自体は5年と短かったようだが、いつしかこの場所がネオン街に発展し、三宮の夜を代表する繁華地なるのだから時代の流れとは恐ろしい。競馬マニアにいわせると、S字に曲がる東門街の通りこそが、コース形態を留めているらしい。
さて、今回はそんな東門街の一軒を書く。店名を「舟櫓(ふなやぐら)」と言い、安藤伸二郎・喜子夫妻が営む割烹である。店に入ると、カウンター越しにあるおばんざいに目が行く。「瀬戸内小蛸煮」「茄子の味噌炒め」「大和野菜丸茄子揚出し」「うの花」「入梅鰯煮」などなど、その惣菜の多さに目移りしそうだ。三段の棚にズラリとおばんざいが並んでいるし、その右や、左の冷蔵ケースの上にもある。女将の安藤喜子さんによると、「日によって異なりますが、日替わりで15品以上は並べてあり、常連さんも飽きる事がありません。大半の人はここから3〜4つを選んで注文し、それにプラスして色んな料理を食します」。中にはおばんざいばかりを好んで注文する顧客もいるようだ。これだけ多くのおばんざいを開店前から作ろうとしたら作業は大変だろう。板長を務める安藤伸二郎さんは「何もなければ、4時間くらいかかる」と話していた。板長は営業時間中にもひたすら何かを作っている。それは顧客が注文した一品料理だったり、おばんざいに加える一品だったりするわけだが、「表(カウンター前)に出る時は刺身を切る時ぐらいかもしれませんね」と笑っていた。皿に盛られたおばんざいは、何も作り込んだ料理ばかりではない。時折柄、空豆や万願寺唐辛子、小芋の絹かつぎなどを置いており、そのうちの空豆は夏は北海道から(正月は九州から)のもので、注文を聞いてから湯がいてぬくぬくの状態で供す。小芋の絹かつぎも奄美大島や鹿児島のもので、これまたヘタを取って湯がいて出すそうだ。このように素材を見せて注文を促して調理するのも「舟櫓」らしさ。いいものを仕入れなければ、そんな売り方もできないので、安藤伸二郎さん曰く「少々仕入れ値が高くても産地のものを買って来ている」との話であった。そんなおばんざいの中で目を惹く品が一つ。「いわしのみぞれ煮」が一際存在感を放っていた。どうやらそれは「舟櫓」いち押しのおばんざいらしく、大きな塊を天ぷらにしたように見受けられる。「鰯を開いて中にネギを入れて野菜を巻き揚げているんです。天だしに漬けて大根おろしで食べるんですよ」と教えてくれた。塊のままだと大きくて食べにくいだろうから切って出すのだとか。安藤伸二郎さんは「分量は同じでもカットすると、陳列のイメージが湧いて来ない。皆さん、コレ何?って感じの顔をします。そのギャップが面白くて…」と茶目っ気ぶりを漂わせる。そんな顧客との関係性が「舟櫓」のいいムードを作り上げていると思った。




安藤喜子さんの話では、もともと「舟櫓」は今よりも割烹然とした店だったらしい。創業は昭和63年(1988)でその昔は彼女のお母さんが経営していた。当時は活けの魚中心の割烹料理だったようで、今よりも全体的に価格が高かったそうだ。不動産屋や建築関係、製品会社などの接待にも活用されていたという。バブル期はそれなりの繁昌ぶりを見せていたものの、1990年にはバブル経済が崩壊。追い打ちをかけるように1995年には阪神淡路大震災が神戸を襲う。流石の繁昌店もそれには耐え切れず、半年間休業して一時は生田新道で屋台営業をするまでに追い込まれた。それでも2000年6月には店を全面改装して再スタート。安藤喜子さんによると、「代替わりもしたし、丁度いい機会だったのでコンセプトを変えて、おばんざいもある親しみ易い割烹へと変貌した」ようだ。今ではそれが当たり、身近にあっただろう、おばんざいを求めて顧客がやって来る。男性客が7割を占めるらしいが、特に単身赴任者など、一人暮らしは、この手の料理に飢えているのか、かつてのおふくろの味を想像すべく、おばんざいで一杯飲るシーンが見られる。
厨房を司る安藤伸二郎さんは、鹿児島生まれだが、幼い頃にすでに神戸に来て育ったので生粋の神戸っ子といってもおかしくはない。三宮にあった「二鶴寿司」で寿司職人としてスタートし、その後大阪や堺などの割烹に転じて板前修業をした。「舟櫓」がオープンした頃は二番手として厨房で働いていたそう。安藤伸二郎さんは、何にでも挑戦したい性格みたいで、手打ちそばもメニュー化している。ご飯が終わってしまい、寿司代わりに食べるかと出したのがきっかけで、以来メニュー化したという。そのために独自で一年間そば打ちを勉強し、そば屋にも負けぬ一品を出している。「福井のそば粉がいい。特に新そばは緑色がきれいで旨い。夏そばは8月すぐに出回るが、量が少ない。むしろ11月のそばの方が好きですね」と話していた。料理だけでは飽き足らず陶芸の道も極めている。奥さん(安藤喜子)は「家に窯を作って焼く程の熱の入れよう」とあきれるほど。25歳からやり始めたらしいが、一時期中断し、40代になってから再び熱を帯び始めたそう。立杭に通って陶芸の勉強をし、店で使う器などは手作りしている。そればかりか、同じ湯呑みを何十個も作って欲しいという人にあげているのだとか。ここまで来れば脱帽せざるをえない。
間違って届いた「赤だし」味噌を高評価

「舟櫓」は、喧繰な東門街本通りから一本入った路地に佇む。その奥は生田神社で、まさに生田神社そばの隠れ家的要素を持った店だ。白木のカウンターがズドンとあってそこに9席。その横に掘り炬燵式の個室が三つある。料理はカウンター前の鉢に盛られたおばんざい。造りや揚物や煮物などの一品料理、鍋もあっておまけに寿司もあるという陣容だ。酒は焼酎と日本酒が中心で、カウンター奥にお薦めの日本酒が貼ってある。安藤伸二郎さんは、「せっかく湯浅から色んな調味料を送ってもらったので、今日はいくつかのおばんざいに試してみました」と言っていた。その一つが「白搾り」を用いた「うの花」で、いつもは淡口醤油を使用するところを、今回は白醤油で_。『白搾り』は塩分が少ないので優しい味に仕上がったと表現していた。それ以外にも「いわしの生姜煮」に「樽仕込み」を使って調味していた。


今回、「舟櫓」が特別に本取材用にと作った和食は、「茄子の味噌和え」と「鮎の金山寺焼き」である。前者には「白みそ」「赤みそ」「赤だし」の三つの天然醸造の味噌を使い、後者には文字通り「金山寺味噌」が使われている。まず「茄子の味噌和え」だが、これは長茄子を揚げて鶏みそを掛けて作ったもの。鶏ミンチ肉を炒めて、そこに「白みそ」「赤みそ」「赤だし」を加え、少しの砂糖と、みりん、玉ネギのみじん切りを入れて直火で1時間弱ほど煮て作っている。それを湯を掛けて油抜きした長茄子に和えて味わうのだ。安藤伸二郎さん曰く「丸茄子だと中が柔らかくなりすぎるので長茄子を用いた」らしい。茄子だけだと物足りない気がして鶏ミンチも加えて中華風にならぬよう工夫したようだ。「白味噌は甘みを出す役割で、赤味噌はコクを出すために使っています。赤味噌だけだとどうしても辛くなるので、それを緩和させる役目で赤だしを足したのです」と言っていた。初めは「白みそ」と「赤みそ」だけで作ろうとしていたらしいが、発注ミスで「赤だし」が届いてしまった。余分に届いて使うつもりのなかった「赤だし」の味がいたく気に入り、優しい味がうまくはまると思って三種の味噌で鶏みそを仕上げている。一般的に「赤だし」といえば八丁味噌で、豆ばかりで造る事からどうしても苦みが生じる。今回の「赤だし」は、米に麹菌をつける米味噌で三年寝かせているためにマイルドな味わいがし、苦みも少ない。米麹を多く使い、塩分も8%と控えめなので渋みや酸味も少なく、まろやかな深いコクと旨みを醸し出しているのだ。今回メインに使用した「白みそ」も高く評している。「若い頃は西京味噌をよく使ったものですが、それに比べてこの『白みそ』は田舎味噌の雰囲気を宿しており、そこまで甘く感じませんでした。なので砂糖をほんの少し足しました。どうしてもみりんを足しているので、その水分を飛ばす意味でも煮込み時間が1時間近くかかるんですよ」。安藤伸二郎さんに言わすと、「鶏みそは『白みそ』と『赤だし』だけでも成立した」ようだ。ところが、「赤みそ」を加える事でコクが出て、色も赤く映って旨そうなのでプラスしたという。



次に「鮎の金山寺焼き」の説明を。夏というのと、和歌山の印象よろしく、「舟櫓」では本取材用に鮎を用いる事にした。使用しているのは、徳島の鮎喰川(あぐいがわ)の鮎である。安藤伸二郎さんの話では「最近は鮎を食べる人が少なくなった」とか。天然ものも手に入るけれど、なぜか人気がないので料理屋でも出す所が少なくなったそうだ。「舟櫓」でも、時折り鮎の塩焼きや棒寿司を出すくらいだという。「届いた商品に『金山寺味噌』があったので、鮎の金山寺焼きを思いついたんです。作り方はいたって簡単で焼いた鮎に金山寺味噌を和えたものを載せるだけ。金山寺味噌だけだと辛く感じそうなので酒粕と砂糖と煮切り酒を足して和えました。砂糖で甘みを持たせ、煮切り酒でコクをつける。そこに酒粕を加える事でマイルドになる」という。「和えてすぐよりかは、1〜2日ほど寝かせた方が味がなじむんです」とも。意識して食すと酒粕があるのがわかる気はしないでもないが、なじます事でその味は徐々に消えて行くのだと説明してくれた。意外にもこの酒粕がいい役割を演じているように思えてならない。安藤さん夫妻は神戸の人なので、あまり金山寺味噌になじみがないらしい。ただ送られて来た「金山寺味噌」を口に入れて金山寺味噌の認識が少し変化したようだ。「今まではあしらい程度に添えるのが関の山。今回のようにメインで調味する事はほとんどありません。この手の大粒のものは余り見た事がなく、初めて旨いと思いましたね。今回のように調味料使いもいいかもしれません。また個人的にはなめ味噌として(冬になると)兵庫県の岩津ネギにつけて食べると旨いでしょうね」。



前述したように「舟櫓」では、多くの客がカウンターのおばんざいをいくつか注文し、造りの盛り合わせや揚物を中心に一杯飲るケースが多い。おふくろの味的なものを求めて来る一人客もいれば、会社帰りに寄って一杯飲る向きも少なくない。安藤喜子さんは「近年は女子会仕様も目立って来た」と言っていた。オヤジ女子の利用もさる事ながら安藤さん夫妻が作り上げる店の雰囲気に女性達がなじんで来た証しでもある。コロナ禍は当然大変だったようだが、それ以降女性客も増えたならコンセプト変更後の店づくりは成功したように思う。「三年前に神戸名店百選に選ばれました」と安藤喜子さんが言っていた。これは阪神淡路大震災と新型コロナウイルス感染症という二度に亘る未曾有の危機を乗り越えて存在し、神戸市民に愛される飲食店を讃えて神戸市が表彰したものだ。受賞店リストには老舗の名がズラリと明記されている。その中にあって「舟櫓」が一緒に選出されているのは、すでにこの店が老舗の域に入った事を物語っている。
-
<取材協力>
舟櫓
住所/神戸市中央区下山手通1-3-12 ゼウスタウンビル1階
TEL/078-331-5517
HP/ 公式HPはこちら
営業時間/17:00〜23:00
休み/日曜日、水曜は不定休
メニューor料金/
肉じゃが煮 770円
胡麻とうふ 770円
いわしのみぞれ煮 990円
なすの味噌炒め 770円
小あじ南蛮漬 660円
むかご芋 660円
絹かつぎ 880円
そら豆 770円
造り しまあじ 1870円
造り 剣先 1870円
造り はも湯引き 1870円
鯨 尾の身造り 1980円
寿司 にぎり盛り合わせ 2090円
珍味 さばへしこ 1100円
おこぜ唐揚 1870円
淡路小海老唐揚 990円
伝助穴子天ぷら 2200円
国産牛サーロインステーキ 2600円
播州赤鶏塩焼 1430円
※料理は日によって替わる
筆者紹介/曽我和弘
廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。