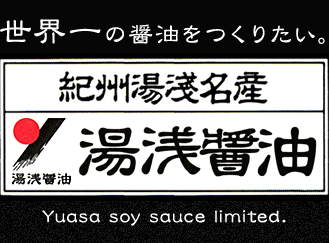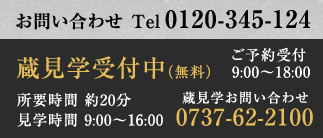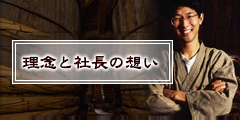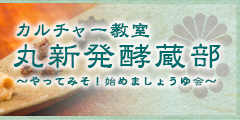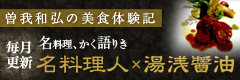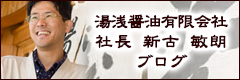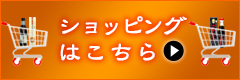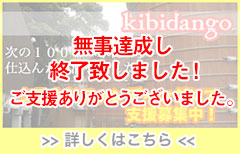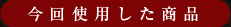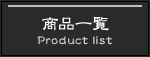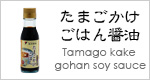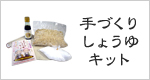143 2025年09月コシの良さを求める讃岐うどんとは違って、大阪うどんはツルッとした喉越しで、麺がモッチリしているのが特徴。その歴史は古く、四百年以上とされ、麺だけではなく、だしにもこだわりを見せる。北摂で多くの店を有す「太鼓亭」もそんな大阪うどんの代表格。水上泰輔社長も「もっと大阪うどんをPRすべく、メニューにも大阪色を掲げたい」と語っている。そんな「太鼓亭」の四店舗で、泉佐野市とコラボして作った一品料理が話題になっている。今夏から始めた泉だこと水茄子を天ぷらにして出すその商品は、産直で素材がいいからか、飛ぶように出ているのだ。今回は、泉佐野産水茄子の天ぷらに付随して「名料理、かく語りき」の取材を行う事にした。取材時に出て来たメニューが、余りに出来がいいので9月の新メニューとして登場するそうだ。
太鼓亭 服部緑地店 小原友行
(「太鼓亭」店舗開発部リーダー)
 「湯浅醤油の『樽仕込み』は、
「湯浅醤油の『樽仕込み』は、
塩角もなくてまろやか。
だしに使ってみると、
甘みを感じました。
深みのあるだしになりましたよ」
泉佐野産(もん)の水茄子とタコを使った一品メニューが好評



第141回の「食の現場から」でもレポートしたが、水茄子の調理汎用が拡大化している。これは泉佐野市の「泉佐野産(もん)普及促進事業」の一環として始めたものだ。同市第一の産物とまでいわれている水茄子のブランド化を進めるべく私が行っており、何人かのシェフ達にその使い道を提案してもらっている。泉佐野産の水茄子は、今や全国にその名を轟かせる野菜だが、大半が生か、浅漬けと相場が決まっている。ところがシェフ達に検証させると、調理素材として捨てたもんじゃなく、なかなか使い勝手がいいらしい。なので私も自信を持って水茄子の調理汎用性を謳える事ができるのだ。特に天ぷらは秀逸。長茄子の天ぷらも旨いのだが、揚げると実はスポンジのように沢山の油を吸収してしまう。だからどうしてもしつこく感じざるをえない。でも水茄子を天ぷらにすると、そのしつこさが軽減される。いや、カラッと揚がって脂っぽさが全くないとも言えよう。原因は水茄子が持つ水分にある。実の中の水分が油の進入を遮ってしまうのでスポンジのように油を吸い込まない。シェフ達が口を揃えて言うのは、「天ぷらにすると、長茄子より断然旨い」との台詞。名のある料理人達がそう薦めるのだから間違いはない。
それを受けて「太鼓亭」で水茄子の天ぷらを出してみようかとの話が持ち上がった。事の発端は昨秋、私が「太鼓亭」本社に稲田敦士専務を訪ねた事による。稲田さんは、以前から練り物でいう天ぷらを店で出したいと思っていたらしく、漁協に未利用魚の使い道として提案してくれないかと相談していた。泉佐野市役所を通じて泉佐野漁協に当たってはみたが、その加工場の有無が問題らしく、具体的には練り物の話が進みにくかった。それでも「一度漁協を覗くだけでも何かヒントがあるかもしれない」と稲田さんら「太鼓亭」スタッフを泉佐野漁協へ誘ったのである。
泉佐野漁協では、組合長の三好正広さんが丁寧な対応をしてくれた。三好さんの話では、「加工場の見つけにくい未利用魚の練り物よりも、いっその事、泉ダコを直仕入れしたらどうか」と言っていた。泉ダコは、広く知られたブランドだし、漁協では一般セリに出さないので、回し易いと思ったのであろう。新鮮なタコが入れば、いい揚物はできるであろうし、顧客もタコの天ぷらは好むで注文するだろう。「もし漁協からの直仕入れが可能なら、ぜひともやりたい」というのが「太鼓亭」の思いであった。「太鼓亭」グループは、現在ファミリーレストランタイプの「太鼓亭」が四店舗あって、その他に「そば太鼓亭」や「うどん食堂TAIKOTEL」「金比羅製麺」の四つのブランド店がある。稲田さんは、セルフタイプの店舗数が多い業態でやるより前にフルサービスの「太鼓亭」で導入するのがいいとの判断だった。ならば、泉ダコの天ぷらと同時に泉佐野産水茄子の天ぷらもやればいいとアドバイスをしておいた。後日、「太鼓亭」のメニューを作っている店舗運営部の小原友行さんに聞くと、「タコはともかく、茄子の天ぷらがそこまで需要があるのだろうか?」との声も聞かれたらしい。稲田さんや商品部購買担当の東將樹さんらは、「せっかく泉佐野市役所(泉佐野産普及促進事業)とのコラボも可能なので、ぜひ進めたい」と言って強行した。




7月下旬から「泉だこの天ぷら」と「水茄子の天ぷら」を「太鼓亭服部緑地店」でスタートし、直仕入れのルートを確立した上で豊中春日店・伊丹中野店・吹田金田店でもメニュー化した。今回「名料理、かく語りき」の取材は、そんな前段階を受けてのもの。だからこの後、泉佐野産水茄子を使った「水なすと豚バラ肉のつけ麺」が登場する。
取材日に「太鼓亭服部緑地店」に行くと、小原さんからの第一声は「すごい反響!」との驚きだった。聞けば、「泉だこの天ぷら」はサイドメニューとして置いてあるのだが、これまで断トツ売れていた鶏の唐揚げを抜き去った出卓数が出ているとの話であった。鶏の唐揚げは、スタンダードに人気あるメニュー。どこの店でも出るのはわかっている。それをあっさり抜き去ったのだから「泉だこの天ぷら」の反響は凄いとしか言えない。「タコは食感が出るようにあえて大きめにカットしています。細かく切ったら美味しさが伝わらないのです。低温で茹でて衣をまとい、揚げています」と小原さん。食べると、漁港直送だけに鮮度も高く、歯応えもある。噛み締めると、タコの旨みが十分伝わって来るものであった。確かに泉ダコはブランドである_。でも明石ダコほどの知名度ではない。タコ好きがいくら多くとも鶏の唐揚げを抜く事は考えられないだろう。単品550円(税抜き)はお値打ちだが、やはり味がいい事が最大の理由だと思われる。小原さんも「リピーターが続出しています。当店としては手が出し易い値段で提供したのですが、それよりは素材の良さ。食べて旨かったからリピートするのだと思います」と語っていた。
泉佐野の水茄子農家から届く水茄子もやはり鮮度抜群。こちらも流通を通さずに農家から「太鼓亭」に直送。だからスーパーや八百屋よりいち早く水茄子が届けられている事になる。「太鼓亭」の各店舗では、農家直送の水茄子に薄い衣をつけて揚げている。タコは少し厚めの衣にしているのに、水茄子は薄衣で。その方が果肉の柔らかさが伝わっていいのだとか。購買担当の東さんも「せっかく鮮度抜群でいい水茄子が届いているのだから、その良さを伝えなくては...」と新商品に自信を窺わせている。前述したようにスタッフからは茄子の天ぷらがそんなに売れるものだろうかと疑問があったのは事実。ましてや長茄子ではなく、水茄子の天ぷらなんてどこにもないと思ったのであろう。ところがいざ商品化してみると、よく出るばかりか、リピート率も高い。これは水茄子に調理汎用性がある証で、泉佐野市農林水産課とのコラボを実現しようとした稲田さんら本社スタッフの先見の明でもあるのだ。...とはいえ、「太鼓亭」本社では、どのくらい出るのか、産地直送の品がうまく届いてどのようにしたら各店舗に行き渡るのかをチェックしたい考えもあったので、今年はフルサービスシステムの「太鼓亭」四店舗で出すに届めた。これだけ反応がよければ、来年は「そば太鼓亭」や「うどん食堂TAIKOTEI」といったセルフサービスの店でも泉佐野産の産物がお目見得するかもしれない。そんな期待を覗かせる「太鼓亭」の“泉佐野フェア”であった。
だしに「樽仕込み」がマッチし、深みのある味に



ところで「名料理、かく語りき」なのだからいつものアレはどうなったのか?。今回もやはり湯浅醬油・丸新本家からいくつかの商品を「太鼓亭 服部緑地店」へ送ってそれらを使用したメニュー例を作ってもらった。担当するのは前出の小原友行さん。彼は本社では店舗運営部に属し、主にフルサービスの「太鼓亭」のメニュー開発を任されていると同時に、服部緑地店の店長も兼任している。小原さんは、吹田の出身で昔から「太鼓亭」には両親と一緒に食事に行っていたらしい。実家が市場で漬物屋を営んでいた事もあって食関係には切っても切れない縁があったのだろう。大学四年生時に、いざ就職をとなった折りにも両親も「太鼓亭がええのでは...」と薦めてくれたという。たまたま募集が出ていたのと、地元企業だったのもあって募集したらうまく受かったのだという。「その時は新入社員が20名入りました。一年目は仕事を覚えるべく厨房とホールの往復で、単に慌しく時が過ぎて行きました。二年目からは厨房の仕事をじっくりと行い、だしの摂り方などを勉強。調理に関する事なので素人には難しく、時間もかかりましたが、それが今になって役立っているのだと思います」と話してくれた。店長になったのは高槻大塚店で、以降色んな店で仕事をし、商品開発を任されるまでになっている。
服部緑地店は、1985年にオープンしており、「太鼓亭」の歴史の中でも六番目に開いた古い店となっている。服部緑地駅から車で10分ぐらい、岡町駅からでも10分くらいの中間地点にあって住宅街に建っている。服部緑地もすぐに近くにあるが、近隣に家もあるからだろう、徒歩または自転車で訪れる人も多い。「ここは『太鼓亭』の中でも忙しい部類に入ります。古くからの顧客が多く、三世代に亘って利用してくれています」と小原さん。特にお盆は近くの墓参りに出かけ、帰りに立ち寄るのがルーティンになっているらしく、私が取材に行った15時でも車が何台も止まっていた。
そんな服部緑地店なら「太鼓亭」らしいメニューも生まれ易いのか、7月下旬からやっている泉佐野フェア(他の三店舗も実施している)は、常連客にもすんなり受け入れられて高い評価を得ている。本来なら「泉だこの天ぷら」と「水茄子の天ぷら」は、塩か天つゆで食べるのだが、今回は「名料理、かく語りき」の取材もあって小原さんが湯浅醤油の「柚子梅つゆ」を厨房から持って来てくれた。揚げたての天ぷらに「柚子梅つゆ」を掛けて食べると、酸味がついて、これまたあっさりと味わえる。稲田さんによると「ダイレクトに掛けても旨いが、当店のだしに『柚子梅つゆ』を落としてそこに天ぷらを浸すと、かなり旨い」との話であった。だしは鰹節、昆布、いりこ、雑節など複数をブレンドし、さらに追い鰹をして作っているそう。複雑な旨みの中に「柚子梅つゆ」の香りと酸味・旨みが加わり、いい天つゆが出来上がる。泉佐野産のタコと水茄子の天ぷらをそんな味わい方で楽しんだ。




取材日には、さらにもう一つ、泉佐野産水茄子を用いた新たな一品が登場した。商品名は、泉佐野産「水なす」丸ごと使用「水なすと豚バラ肉のつけ麺」で、小原さんによると、この取材も兼ねて試作したばかりで、9月の新メニューとして「太鼓亭」で提供しようかと思っているとの話であった。同商品は、見た目にもユニークで、タイトル通り泉佐野産の水茄子を丸ごと揚げているのが特徴。「ヘタを落とし、尻もカットして安定性を持たせて盛り付けしています。それを豚肉が入っただしの上に盛って出すつもりで考えています」と小原さんが説明してくれた。だしはざるそばのつゆをうどんのだしで割って作っている。そこに水茄子と相性のいい豚肉を入れているのだとか。中央に盛った丸ごとの水茄子天ぷらは、生の状態で8回包丁で切れ目を入れて揚げているから箸を入れると、すっとほぐれる。水茄子の天ぷらには天盛りで大根卸しと刻み大葉とみょうがが_。水茄子をほぐすと、それらもだしの中に浸り、うまく調和する設計になっている。そのだしに細うどんを加えて漬け麺風に食して行く。「だし自体は漬け麺で食す濃さなのですが、水茄子をほぐすと、水茄子の水分がだしに染みて薄くなりすぎません。だしまで味わえるイメージで食べて欲しいですね」と言う。小原さん曰く、「これが長茄子だとしつこさがあるばかりか、茄子自体に水分がないので辛くなる」そうだ。「それが水茄子だと、だしの味も染みすぎず、茄子の味そのものも残っていいんです。瑞々しさと火に掛けた旨さの両方を楽しめるから秀逸です」とも。


本取材もあったので、この日は湯浅醬油の「蔵匠 樽仕込み」を用いてだしを作っていた。小原さんは、「湯浅醬油の『樽仕込み』は、塩角がなく、嫌みがない醤油で、だしに使うと丸くなって甘みを感じます」と評しており、今回「水なすと豚バラ肉のつけ麵」に使ってみたら、いつものだしより甘みを感じたと話していた。確かにだしだけを飲んだ時に深みがあって麺ともよく絡んでいたように思う。「太鼓亭」では、この試作の出来映えがよく、スタッフからの評判もいいので、9月から四店舗で売り出す事を決めた。「今年の9月に出してもメニューとして本格派させるのは来年かもしれませんね。せっかく泉佐野の農家とパイプができたのだから、積極的に広報したいですね」と東さんも意気込んでいる。7月から行われている「太鼓亭」の「泉佐野フェア」は、店側も期待値を込めて企画している。昨今、産地直送を謳っている所は多々あるが、「太鼓亭」の「泉佐野フェア」は、そんじょそこらの産直ではなく、農家や漁港とタッグを組んで行う本格派。以前、「太鼓亭」の水上泰輔社長が「せっかく大阪うどんを掲げているのだから、もっとメニューに大阪らしさを持たせたい」と言っていた。ならば、今回のメニュー化は、目指すイメージの先駆けとなるのではなかろうか。行政の泉佐野産(もん)の取り組みから端を発して地元農家や漁協が動き出し、その末に大阪の飲食店で素材をいかしたメニューが誕生している。これは一つのバタフライエフェクトに違いない。
-
<取材協力>
太鼓亭 服部緑地店
住所/大阪府豊中市夕日丘3-6-15
TEL/06-6856-2200
HP/ 公式HPはこちら
営業時間/11:00~23:00(LO22:30)
休み/無休
メニューor料金/
肉カレーうどん定食 999円
太鼓天盛り定食 999円
梅とじうどん定食 999円
肉うどん 1089円
鍋焼きうどん 1210円
黒酢の酸辣湯うどん 1089円
穴子天おろしそば 1100円
和風ちゃんぽん 1089円
海老天ねばとろそば 1078円
肉カレーうどん 1045円
泉だこの天ぷら 605円
水なすの天ぷら 385円
※価格は税込み
筆者紹介/曽我和弘
廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。