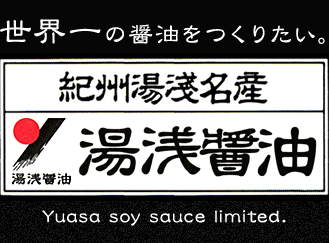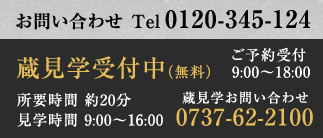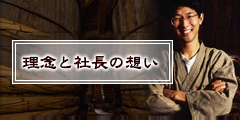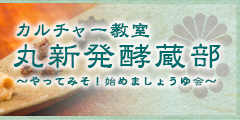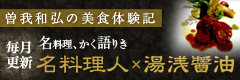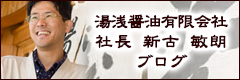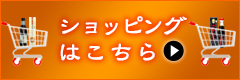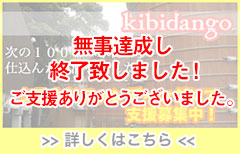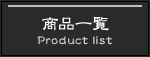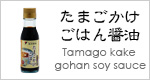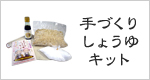144
夏といえば、涼しげなものを欲したくなる。日本料理においてよく使われる蓴菜(じゅんさい)がその素材の代表格。会席料理では前半に出て来る事が多く、ガラスの鉢に水を注ぎ、そこに蓴菜を浮かべる様を思い出す人も多かろう。造り替わりのような使用の多い蓴菜だが、その大きさにもまちまちあって料理によって大小を使うケースが異なるらしい。三田(兵庫県)に蓴菜のコースを出す店があるという。聞けば、蓴菜づくしになっているらしく、夏のみに提供しているそうだ。ならば一度は体験せねばと、車を走らせた。竹林の中に佇む「ぬなわや」では、普段なら6月から8月までの蓴菜の懐石料理(茶懐石に基づく料理)を出ている。今回は、私が食べて来た蓴菜料理のレポートを載せる事にする。
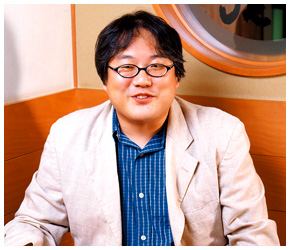
- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。
あのツルンとした食感が涼を誘うのだ


今年の夏は、とにかく暑かった。猛暑、酷暑とはよく言ったもので、数年前に熊谷で体温ぐらいになったと驚いたのが噓のよう。大阪や東京でも体温ぐらいの気温は今や当たり前で、40℃なんて記録している日もあって、このままだと来年はさらに思いやられる。あまりの暑さ故に当方の食欲も減退気味で、この夏に食べたものといえば、冷麺にざるそば、寿司ぐらいしか記憶にない。某日本料理店では、土日のアイドルタイムにかき氷を提供したところ、飛ぶように売れたという。とにかく冷たいものか、ツルッと喉を通るものしか食べたくないのだ。
今夏、食べたもののうち記憶に残っているのが蓴菜(じゅんさい)。その専門店が三田にあって蓴菜のフルコースを出しているとの話だったので、勉強も兼ねて食事に行った次第である。蓴菜は沼や池に生える植物で、ぬめりがあるのが特徴。ぬめりには酸性多糖類が含まれていて光合成が活発に行われていれば分泌される。だからぬめりが多い程いい蓴菜だといわれているのだろう。そもそも蓴菜は、スイレン科の多年生の水草。水底の地下茎から伸ばし、葉を水面に浮かべる。古くは「ぬなわ」と呼ばれて沼に生える様が沼の縄に見えた事からそう呼ばれていた。専門家に話を聞くと、春に越冬した地下茎から発芽し茎から細長い葉柄を持つ葉が出る。それが夏になると、葉が水面を覆うまで繁るそう。日本では6~8月が花期に当たるらしく、花柄を水面に出して先っぽに花を咲かせるという。蓴菜は池や沼、古いため池で、水深が1~3mある水域に群生する。兵庫県は、昔は池や沼、ため池が多く、自然の蓴菜がよく採れたようだ。なので私達が行った「ぬなわや」では、夏になると蓴菜料理を出して客を迎えているとの話だった。



私達が「ぬなわや」の存在を知ったのはかなり以前。三田に夏期にだけ蓴菜のコースを出している店があると聞き、一度は行ってみたいと思っていた。二年前の6月に「さかばやし」で夏の食材として蓴菜を取り挙げたのをきっかけに専門店ではどんな風に提供しているのだろうと興味を抱いたわけである。その年に噂に聞く「ぬなわや」へ予約を入れたが、「既に蓴菜料理は終わっている」との返事。仕方がないので翌年に再チャレンジする事になっていた。人の記憶とは曖昧なもので、夏になって、それも盛夏が過ぎないと思い出さない。だから一年前も気づいた時はすでに遅かりし。「ぬなわや」では、蓴菜のコースの提供を終えてしまっていた。
この二年間の失敗は繰り返すまいと、夏の始まりから「今年こそ蓴菜料理を食べよう!」を決め、早々に予約を入れたのである。それでも忙しい私達のスケジュールを合わせると、7月の下旬になってしまった。「ぬなわや」で女将(店主)に聞くと、「蓴菜のコース料理は6~8月末まで。でも昨今は温暖化の影響もあって4月末から採れています。だから8月半ばまでくらいの提供になってしまいます」との話だった。危うく今年も食べ損ねる所だったと胸をなでおろした。
三田の「ぬなわや」は、JR広野駅近くにある。近いといっても幹線道路沿いにあるわけではなく、住宅地の小路を入って行くので少々わかりづらい。住宅があると思ったらいきなり竹林があって、その間を縫うように歩いて行くと、「ぬなわや」に到着する。「ぬなわや」は、山里にひっそり佇む茶懐石の店。山里を望む空間で、部屋の窓からは竹林が見える。すべて個室で、たったの三部屋のみ。畳敷きにテーブルを配している。昼夜とも営業しているが、三部屋なので三組の予約で埋まってしまう。店の人に聞くと、蓴菜が終われば10月は松茸コース、11月中旬からは猪のコースが始まるらしい。2~3月は三田の独活(うど)で、3~4月は筍を使って懐石料理を提供しているという。その時々の旬のものを上手く使って茶懐石を提供しているようで、蓴菜以外の季節にも訪れたいと思った。
最初から最後まで全てに蓴菜が用いられている

私達は昼の営業時間に行ったわけだが、蓴菜のコースと聞いて一体どんな風にして調理するのだろうと興味津々だった。正午すぎに店に入り、予め注文しておいた(要予約)昼の懐石コースを味わった。この日出て来たのは、先付・吸物・造り・三田牛の陶板焼・蓴菜の造り・蓴菜の天ぷら・蓴菜の寿司・蓴菜の素麺・すき焼き・肉のご飯・メロン・抹茶の順。勿論、蓴菜のコースだから全てにおいて何かしら蓴菜が使われている。文字で書くとありきたりに映ってしまいそうだが、かなり凄い。料理内容の充実度といい、構成といい、全体の分量といい、満足度120%なのだ。
まず先付には、蓴菜の白和え、湯葉とウニ、三田牛のアキレス腱を煮込んだものがあってなかなか面白い組み合わせになっている。吸物は蓴菜の豆腐。蓴菜を擂り潰して練り込み、葛で固めているらしく、その蓴菜豆腐の周りにも幾つかの蓴菜が浮かんでいる。給仕の女性に聞くと、周りに浮かべているのが一番小さいサイズの蓴菜だとか。中央の蓴菜豆腐は豆腐というより餅っぽい雰囲気で、かなり繊細な味わいだ。


造りとして出されたのが、トロ・鯛・カンパチ。流石にここには蓴菜がないだろうと思っていたら、漬けダレに蓴菜が使われているとか。一般の醤油より柔らかな味で、煎り酒のような雰囲気を持ち、とろっとしている。ここに刺身を漬けて味わうのだ。
三田は和牛が有名な地で、三田牛も神戸牛の中に含まれる事が多い。なのでここではそれを用いている。地元の自慢の三田牛(かなりレベルが高い)を陶板焼きで味わう形で出された。ここでも蓴菜はタレに用いている。バター風味で焼いた三田牛をそのタレに漬けて食べる。タレには蓴菜の他、山椒も使っているとの話であったが、柔しい味で食べ易い。続いて出て来るのが蓴菜の造り_、そう、これはよく日本料理店で見掛けるタイプの一品だ。他店と違うのは、ここでは全ての料理に天然の蓴菜が使われているのと、蓴菜の大きさ。聞くと「椀物に用いたのより大きな蓴菜を使っている」とか。好みでレモン汁を掛け、わさびの入った漬けダレで食べる。


当たり前の話かもしれないが、蓴菜には色んな大きさがある。「ぬなわや」では、一番大きなタイプを揚げて天ぷらで供しているそうだ。カラッと揚がった大きな蓴菜を漬け塩で味わう_。先程の蓴菜の造りといい、この天ぷらといい、ダイレクトに蓴菜の味が楽しめる。蓴菜自体は淡泊で低カロリー。98%が水分だというので、栄養価は少ない。けれど特有のぬめり感やツルンとした食感が何ともいえない。ここでいう蓴菜の造りは、よく目にする料理だが、涼感を表現するのにぴったりで、夏の会席料理によく用いられる理由もわかる。ちなみに普段使われている蓴菜の形は巻いた状態らしく、開いたら一枚の葉っぱになる。
蓴菜の寿司が出て来たので、これがご飯代わりかと思っていたら、どうやら箸休め的に出されているらしい。寿司は軍艦巻きで、各々の具材にイクラ、蓴菜、カニを使っていた。握り寿司(軍艦巻き)の後は、蓴菜素麺。蓴菜の葉と葉の間にある茎を素麺に見立てて調理しており、箸で持ち上げると茎にぬめりが付いているのがわかる。


最後に大物が出来たと思ったら、まだ最後ではないらしい。すき焼きの具材は、鱧・鯛・豆腐・春菊・白葱で、これらを割下で煮込み、具材から汁が出て来た頃に蓴菜を入れる。蓴菜はさっと火を通すくらいでいいらしい。やはり蓴菜づくしのコースなので、すき焼きにも蓴菜が登場するようだ。仕上げは、肉のご飯が_。予め肉とご飯を炊く形式ではなく、「ぬなわや」では、白飯に甘辛く煮た牛肉を混ぜて作り、茶碗によそって食べる。流石にここには蓴菜は用いていなかったが、牛肉がいいのと、その味付が上手いので、かなり印象に残る味わいだった。二人では食べ切れず、残った分を持ち帰る了承をとって土産にした。後は水直しのメロン_、そして場所(部屋)を替えて抹茶を点ててもらった。抹茶には蓴菜の饅頭も付いていた。正午過ぎに「ぬなわや」に入ったのに食事時間は三時を超えている。まさに満足の行く昼食であった。


帰りに「ぬなわや」の女将に話を聞くと、本業は蓴菜の卸しで、瓶詰めした蓴菜などが主流商品らしく、料亭などに卸しているという。「蓴菜の卸しをやってすでに百年も経ちます」と言っていた。先代から引き継ぎ、蓴菜を使って何かできないかと考え、40年くらい前から料理屋も営んでいるそう。「兵庫県下で採れる天然の蓴菜を使用しているのが売り。天然ものは、絶滅危惧種に近いくらい手に入らないんですよ」と話していた。蓴菜というと、今では秋田が主産地で、三種町のものが9割を占めている。ところが、秋田の蓴菜は養殖のものが大半で、天然はほとんどないらしい。「昔は秋田の人も兵庫県に買い付けて来ていたんですよ。先代がアドバイスした事もあって秋田で養殖が始まったんです」と教えてくれた。女将によれば、兵庫県は池や沼、ため池が多く、天然の蓴菜がよく採れたようだ。それが宅地造成などで池が埋められて採れなくなり、おまけに水も良くないので蓴菜が少なくなってしまったと嘆いていた。「気候が暖かくなって採れる時季まで変わってしまう」と言う。
蓴菜は、池や沼の中に生息する。食用にするのは葉が開く前の蕾のような芽の部分で、それを求めて小舟を繰り出し、直接手で摘み採る。私も昔、蓴菜採りを体験したが、それはゴムボートに寝そべって池(沼)の中央まで行って手で採っていた。子供が遊ぶゴムボートだと、なかなか不安定で採るにも不自由。周りの蓴菜が絡まり、岸に戻るのに難儀したのを思い出した。涼しげな風情を醸し出す蓴菜だが、知らぬ事が一杯あって今回はいい勉強になった。勿論、旨い料理にもありついたわけだが...(笑)。